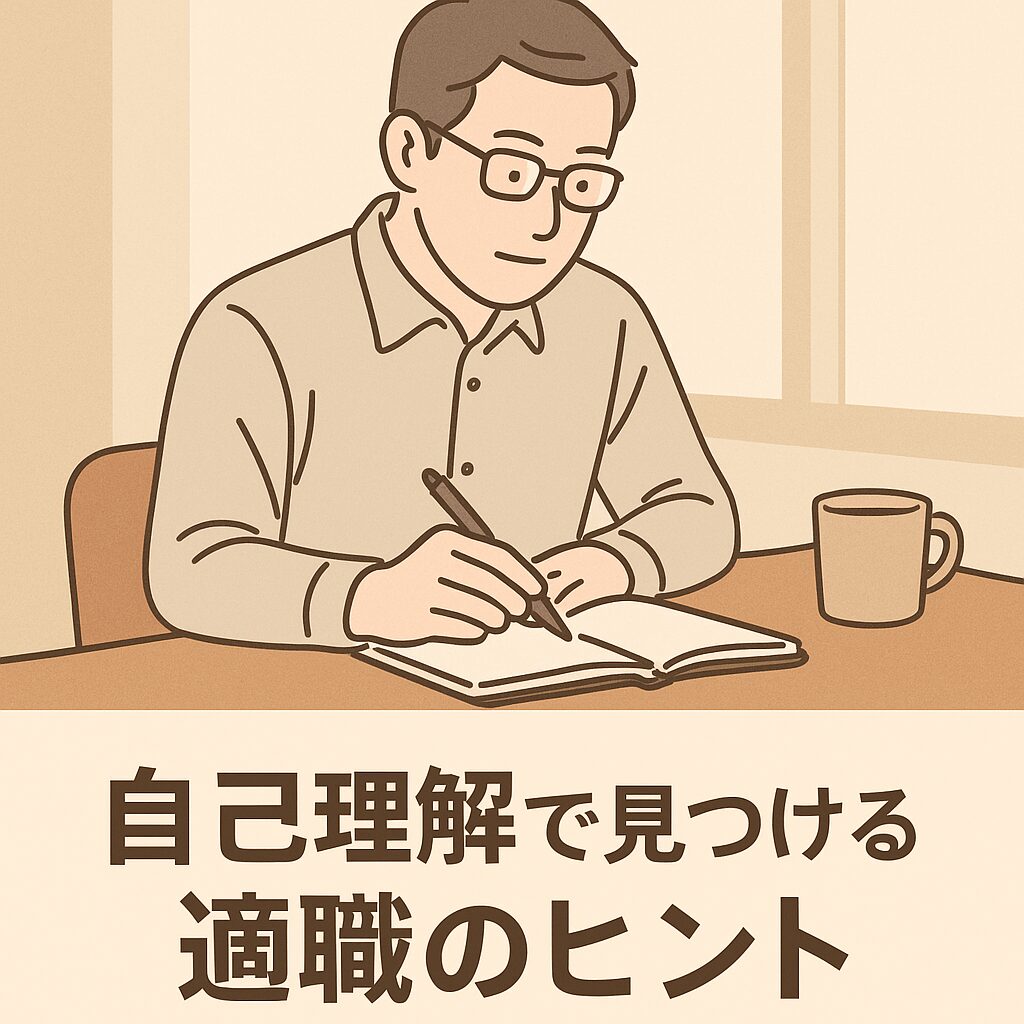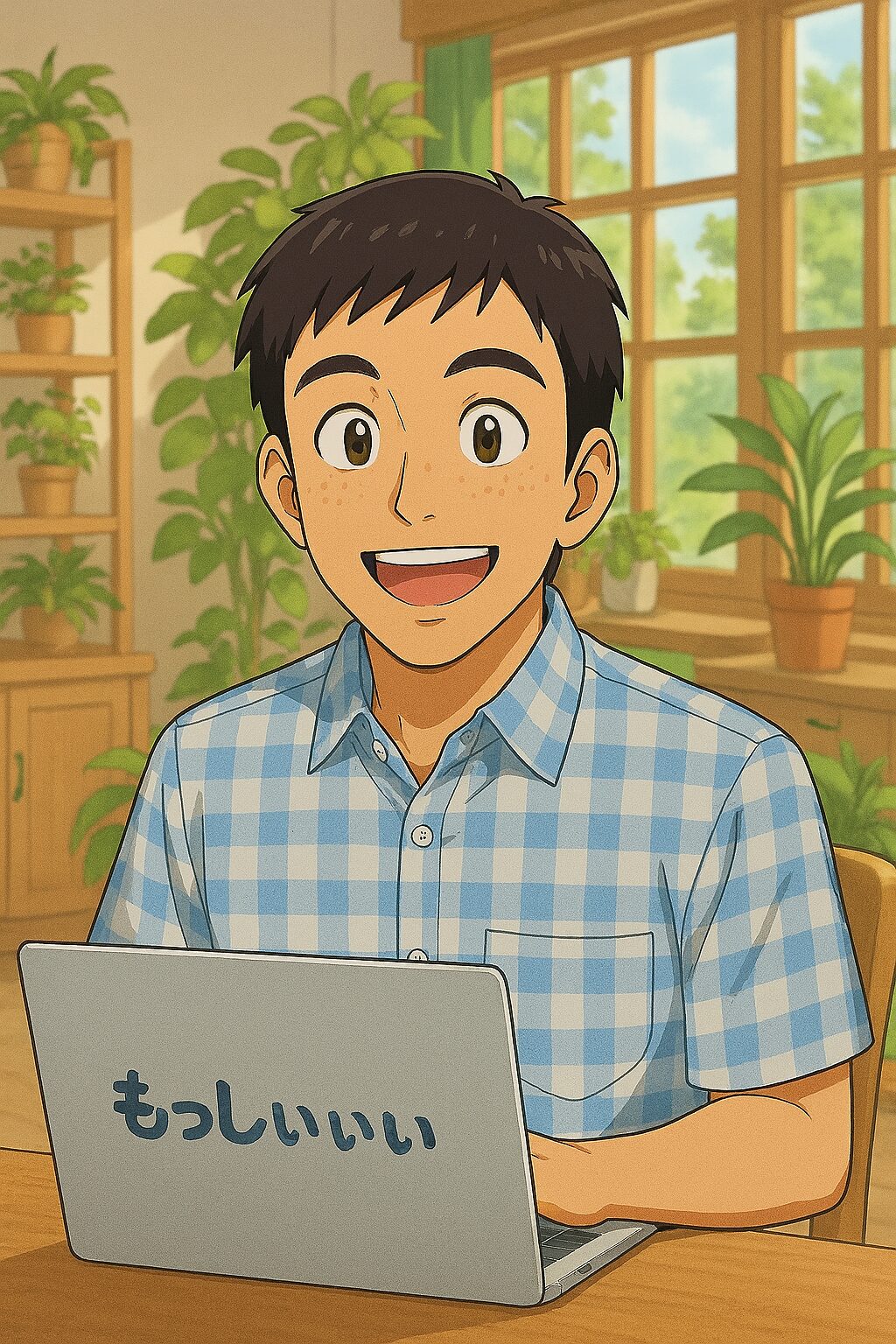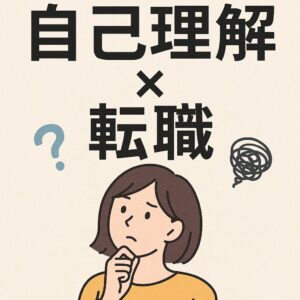―転職を繰り返して見えた、本当の適性―
「得意なのに疲れる仕事」って、
心当たりのある方も多いのではないでしょうか。
これまでの仕事を振り返ると、「自分に合っていた」と思っていた仕事ほど、実は一番しんどかった、そんなことに気づきました。
きっかけは、自己診断で自分の資質や性格を見つめ直したことでした。
(※私は「ストレングス・ファインダー」や「16Personalities(MBTI)」などを活用しました)
診断を通して分かったのは、好きで続けてきた仕事が“本来の自分の適性”とは少しズレていたということ。
私は上位資質(慎重さ・責任感・最上志向など)でなんとか適応してきましたが、
その分、気づかないうちにエネルギーを消耗していたのかもしれません。
思えば、転職を繰り返してきた理由のひとつも、この「得意」と「適性」のズレにあったのかもしれません。
この記事では、診断を通して見えた“自分に合っていると思っていた仕事ほど消耗していた理由”を、私の実体験を交えてお話しします。
これから転職を考える方や、今の仕事に違和感を抱いている方が、
『なぜかうまくいかない理由』を見つめ直し、自分に合った働き方を考えるきっかけになれば嬉しいです。
少しでも、肩の力を抜いて自分らしいペースを見つけるヒントになればと思います。
上位資質で何とかしてきた働き方
まずは自己診断(ストレングス・ファインダー)を読むだけでは内容の理解が難しかったので、ChatGPTに「自分を理解したいので、この診断結果を分析して説明してほしい」と書き込み、内容を整理してみました。すると、自分では強みだと思っていた部分が、実は環境に合わせて発揮していた“適応の力”だったことに気づきました。
自己診断で出た私の上位資質は、慎重さ・適応性・最上志向・達成欲・学習欲・責任感でした。
一見バランスが良く見えるこの組み合わせですが、振り返ると、これらの資質で「無理なくやれていた」ように見えて、実は環境に合わせて必死に適応していたことが多かったように思います。
実際、過去のスキル棚卸しを見返すと、どの職場でも共通していたのは次のようなスキルでした。
- 段取り力・柔軟性・即対応力
- 誠実な対応力と責任感
- 行動力と現場対応力
つまり私は、どんな環境でも「慎重さ」や「適応性」で現場にフィットさせていくタイプだったんです。
現場では信頼を得て、一定の成果も出せていましたが、同時に“無意識の疲労”が常について回っていました。
下位資質の領域で働いていた現実
私の下位資質には、「競争性」「社交性」「指令性」など、いわゆる“影響力系”の項目が並んでいました。
本来であれば、人を引っ張るポジションよりも、落ち着いて考えたり、支えたりする役割の方が向いているタイプですが、それでも気づけば、店長や現場監督など、人をまとめる立場を自然に引き受けていました。
おそらくその背景には、「どうせやるならきちんとしたい」「途中で投げ出したくない」という気持ちがあったのだと思います。
上位資質の責任感・慎重さ・最上志向が組み合わさり、任された以上は最後までやり遂げようとする、現場の空気を読み、トラブルを避けながら全体を整える、そうした動き方が自分らしかった反面、いつの間にか人の分まで背負ってしまうクセも身についていました。
当時はそれを“リーダーシップ”だと思っていましたが、診断を通して振り返ると、それは上位資質が自然に働いていた結果だったのだと思います。
「前に出たい」というより、「きちんと回したい」「誰も困らせたくない」という思いが、結果的に責任ある立場を選ばせていたのだと感じます。
“合っていたと思っていた仕事”の中にあったやりがい
私はこれまで、営業や飲食店、書店チェーンなど、人と関わる仕事を「自分に合っていた」と感じていました。
お客様と直接話したり、チームで動いたりすることにやりがいを感じていたし、「人の役に立てる仕事が自分らしい」と信じていました。
店長として働いていた頃、みんなで目標に向かって頑張る瞬間は本当に楽しかったし、アルバイトが成長していく姿を見るのも嬉しかった。
「自分が関わることで誰かが変わる」という実感は、大きなやりがいでした。
ただその一方で、成果を出してもどこか疲れを感じることがありました。
仕事が嫌いだったわけではなく、上位資質(慎重さ・達成欲・最上志向・責任感)を常にフル稼働させていたかので、理想を追う力と誠実さが強いぶん、心がずっと張りつめた状態だったのだと思います。
気づかないまま“頑張れた理由”
振り返ると、私はどんな職場でも周囲のペースに柔軟に合わせながら、責任を持って仕事をしてきました。
「人のために」「期待に応えたい」という気持ちが強く、途中で投げ出すことができなかったんです。
この人のために全力を尽くす姿勢こそが、私の上位資質が自然に表れていた瞬間だったのだと思います。
自分自身を理解していなかったからこそ、消耗していることに気づかず、いつの間にか限界を迎えていたのかもしれません。
それでも当時の私は、「自然にやれている」と思っていました。
努力が足りないわけでも、気持ちが弱かったわけでもなく、ただ、自分の“エネルギーの使い方”を知らなかっただけなんです。
もともと私は、すぐに気持ちを切り替えられるタイプで、プラス思考だと思っていました。
実際、その傾向は診断結果にもはっきり出ていました。
たとえ疲れていても「大丈夫」と思い込んで動ける。
それが、気づかないまま消耗しても頑張れてしまう要因だったのかもしれません。
強みでもあるその前向きさが、いつの間にか“無理を続ける力”になっていたように思います。
今振り返ると、若い頃の「楽しい経験」を“得意”や“好き”と勘違いしてしまっていたのかもしれません。
「楽しい=向いている」と思い込んでいたからこそ、同じような仕事を選び続けて、気づけば消耗していた。
でも、その経験があったからこそ、今は「本当の適性」を考えるきっかけになったのだと思います。
📘自己理解のきっかけになった1冊
ようやく見えてきた“本来の適性”
診断を通して見えたのは、「得意」と「適性」は違うということでした。
どれだけ成果を出せても、常に無理をしていたのなら、それは“本来の強み”を活かしていなかった証拠です。
私にとって心地よい働き方の条件
- 自分のペースで深く考えられる環境
- 誠実に人と関われる職場
- 一貫性を持って取り組める仕事
こうした環境であれば、「慎重さ」や「学習欲」「最上志向」「責任感」を無理なく使えると感じます。
つまり、強みを活かす仕事ではなく、強みを無理なく使える仕事を選ぶこと。
それが今の私にとっての「合う仕事」なんだと思います。
まとめ|転職を繰り返していたのは「弱さ」ではなく「ズレ」だった
これまでの仕事を振り返って感じるのは、「思っていた自分」と「本来の自分」には少しズレがあったということでした。
ストレングス・ファインダーや16Personalities(MBTI)などの診断を通して、ようやくそのズレの正体に気づけた気がします。
「できる仕事」と「合う仕事」は違う。
「得意なこと」と「続けられること」もまた違う。
これまで転職を繰り返してきたのは、意志の弱さでも飽きっぽさでもなく、
自分の資質と仕事内容の不一致を埋めようとして動いていたのかもしれません。
自己理解とは、自分を責めることではなく、無理して合わせてきた自分を、ようやく労わることなのだと思います。
もし今、「この仕事、自分に合っていないかも」と感じている人へ
焦らずに立ち止まって、自分を見つめ直してみてください。
無理に強くならなくてもいいし、答えを急ぐ必要もありません。
これまでの経験も迷いも、すべてが“これから”を形づくる大切な材料です。
あなたの中にも、まだ眠っている本来の強みがきっとあります。
その強みを信じて、自分のペースで歩いていきましょう。
💡「自分も試してみたい」と感じた方へ。診断コード付きのこちらから始めると、
資質の言語化がスムーズでした。
💡 『選ばれる転職』から『自分で選ぶ転職』へ、そのきっかけになった体験はこちら