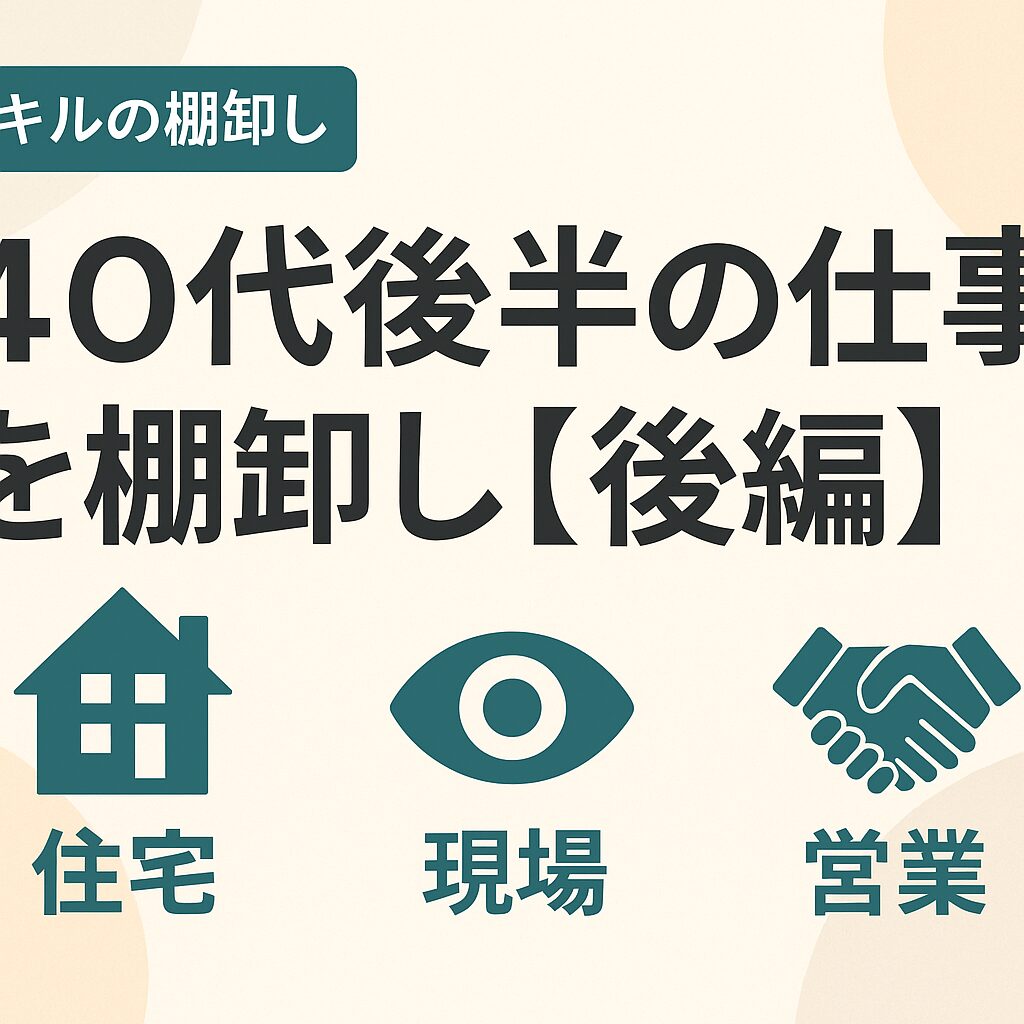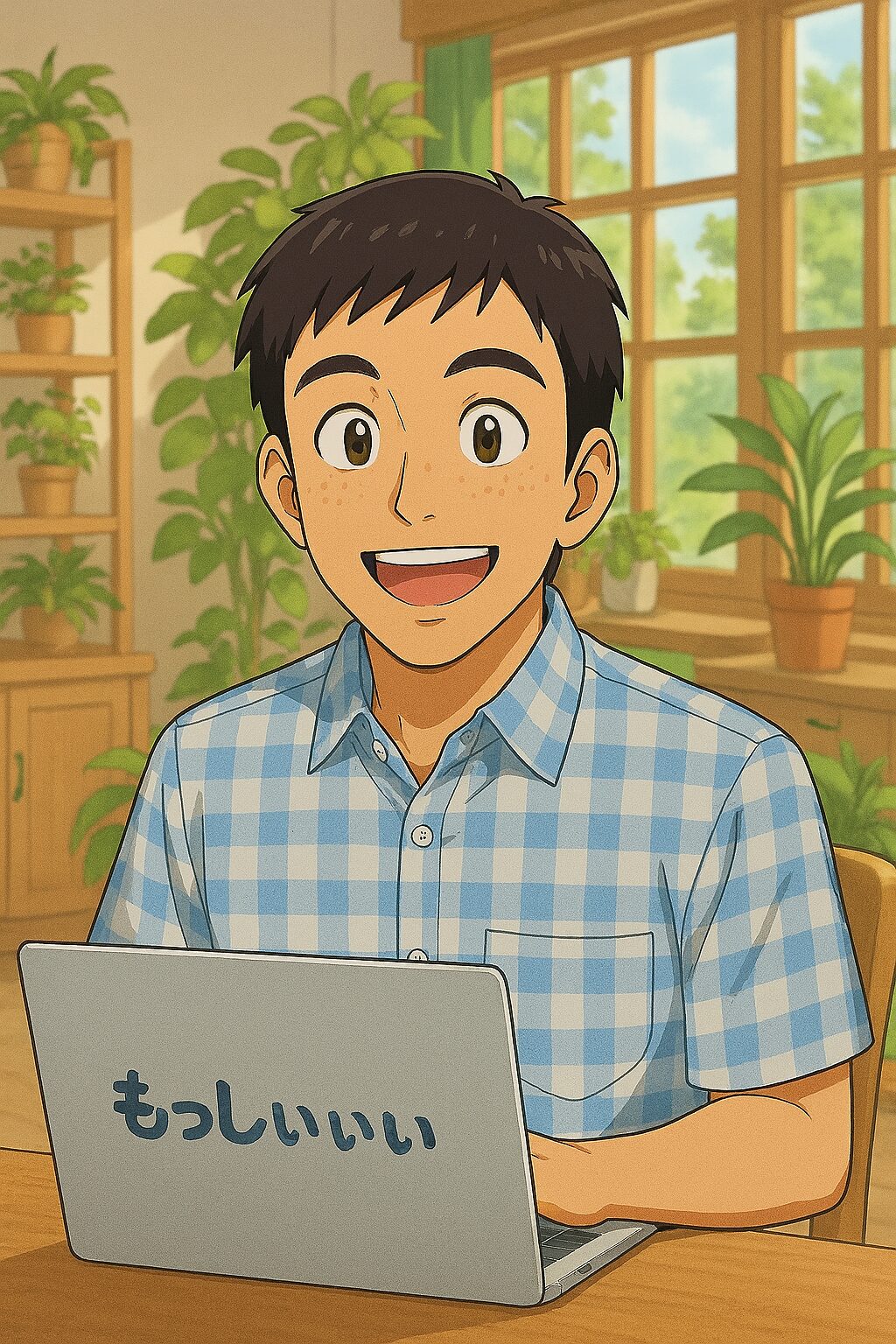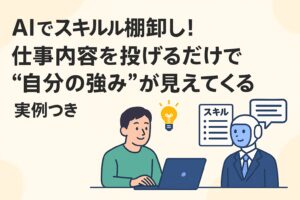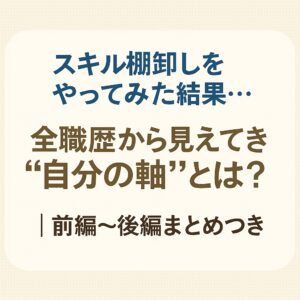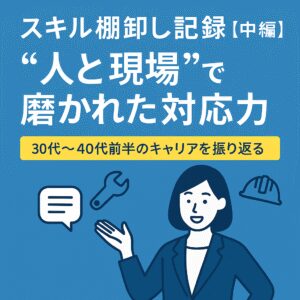さて、スキル棚卸しシリーズもいよいよ【後編】に突入です。
ここからは、私が40代後半〜50歳を迎える頃までの仕事を振り返っていきます。
リフォーム、保険、不動産、建築、資材卸…と、職場も仕事の内容もめまぐるしく変わりましたが、
ふりかえってみると、それぞれの経験が“住宅・現場・営業”という軸で少しずつ重なっていき、気づけば「応用のきく実務力」みたいなものが身についていた気がします。
「もう若くないから」と一歩引くんじゃなくて、“年齢だからこそ通用するもの”がある──そんな感覚も芽生えてきたのが、この時期の大きな収穫だったかもしれません。
🛠 リフォーム専門店で“住宅のプロ”の視点を学ぶ
業界は完全に未経験で、リフォームの仕事についてもまったく知らない状態で入社。
40代中盤ごろのこと。
「人と接する営業なら、自分にもできるかもしれない」という気持ちだけで飛び込んだ私を待っていたのは、建築業界ならではの“言葉と感覚”の世界でした。
「1間(いっけん)=1820mm」「1坪=約3.3㎡」など、今まで使ったことのない単位や表現が次々に飛び交います。
最初は「?」が頭の中に並びっぱなしで、現場で飛び交う言葉についていくのもやっと。正直、軽いカルチャーショックすら感じていました。
まずは座学から始まり、建築寸法の基本やリフォームの用語、主要な住宅設備(水回り機器)の基礎知識を叩き込みます。
TOTO・LIXIL・クリナップなど、各メーカーのトイレやキッチン、洗面台、ユニットバスの特長、グレード、型番による機能の違い…
それまで気にしたこともなかったような項目を、カタログとにらめっこしながら覚えていきました。
同時に、現場調査の仕方も学んでいきました。
お客様宅へ伺った際、どこを測ればいいのか、どこに注意が必要なのか、現場のどんな情報を図面に起こすべきなのか──
これも同行しながら実地で叩き込まれました。現場には現場なりの“見るべき視点”があることを初めて知りました。
この会社では営業と現場監督の担当が分かれていて、私は営業職として勤務。
基本的には、問い合わせのあったお客様への対応が中心でしたが、店舗にはショールームが併設されていたため、
飛び込みで来店されたお客様へのご案内や、その後の見積もり・現場調査への移行なども担当していました。
契約が決まったあとは、工事初日のご挨拶や進捗確認にも顔を出し、現場の雰囲気やトラブルの有無を確認するようにしていました。
こうした一連の流れを通じて、「リフォーム営業」とは単なる物売りではなく、施工現場を含めた総合的な“伴走”であることを実感しました。
特に印象的だったのは、リフォームという商品が「完成品を事前に見せられない」という点。
お客様にとっては完成形が想像しづらく、「これで本当にいいのか?」という不安が常につきまといます。
しかも、リフォームは解体して初めて分かることも多く、予定外の問題が発生することも少なくありません。
その場で判断し、必要であれば内容や金額を調整し、きちんと説明して納得いただく──こうした柔軟な対応力が求められる仕事でもありました。
私は営業として、商品提案から見積書の作成、工事内容の説明、さらには職人さんとの段取り調整まで幅広く関わりました。
「リフォームって奥深いなぁ…」と日々実感しながら、誠実に、正直に、目の前のお客様と向き合うように心がけていました。
ただ一歩間違えると、お客様との信頼関係はすぐに崩れます。説明不足やイメージのズレが原因で、工事後にクレームになるケースもあります。
だからこそ、「きちんと伝えること」「分からないことをごまかさないこと」「話を丁寧に聞くこと」がいかに大事かを、身をもって学びました。
📌 この仕事で得たスキル
- 「1間」「1坪」など、建築業界特有の寸法・用語の理解
- 主要メーカーの住宅設備(水回り)に関する基礎知識
- 現場調査・採寸・図面起こしなどの基本的な実務スキル
- ショールーム接客を通じた「比較・提案型営業」経験
- 問い合わせ対応から契約、工事対応まで一貫した営業経験
- リフォーム工事の流れ・施工現場の特性に対する理解
- 完成形を見せられない商品の説明力と信頼構築力
- 解体後のイレギュラーに柔軟に対応する判断力
- クレームリスクを抑えるための「誠実な対応力と説明力」
🩺 保険代理店で“お金の知識”を武器に営業デビュー
40代中盤ごろのこと。
FP2級を取得した直後、私は「せっかく取った資格を仕事に活かしてみたい」と思い、生命保険の代理店に飛び込みました。
業界未経験だったものの、ライフプランや保障の考え方などには興味があり、「話を聞いてくれるお客様に向き合う営業ならやれるかも」と思ったのがきっかけです。
この会社では、営業とテレアポ部門が分業されており、私の役割は“アポイントを取ってもらったお客様宅へ訪問し、ヒアリング〜提案〜契約までを行う”という流れの営業でした。
訪問先では、家族構成や既契約の保険内容をじっくりヒアリング。医療保険・がん保険・生命保険などの提案を行い、必要であれば保障内容の見直しや新規提案につなげていきます。
FP2級の知識が活かせる場面も多く、保障の仕組みや公的制度との違い、必要保障額の目安など、基礎知識をしっかり伝えることで信頼していただけた場面も多くありました。
……しかし、現実は甘くありませんでした。
この会社の営業方針は「いかに既契約を解約・乗り換えさせ、新規契約をとるか」が重要視されており、
“お客様のため”というより“自分の成績のため”という空気が強かったのです。
初回訪問でヒアリング、2回目で提案・契約という短期決着の営業スタイル。
ゆうちょや共済などの保険や定期保険などのデメリットを伝え、見直しの必要性を感じてもらい既契約の保険をひっくり返す──そんなマニュアルトークが徹底されていました。
「定期保険は、次回の更新時に保険料が一気にあがりますよ」
「必要以上の保障内容になってる可能性もあります」
そんな現場で、自分の中に少しずつ違和感が生まれていきました。
ある日、「もっとお客様に寄り添った営業がしたい」と上司に伝えると、
返ってきたのは「この会社では、寄り添う営業は無理だよ」という一言でした。
──それが、退職を決意した瞬間。
「お金の知識を活かせる」という思いで飛び込んだ世界で、逆に「誰のための営業なのか?」を深く考えるきっかけになった経験でもあります。
📌 この仕事で得たスキル
- 家族構成や状況を踏まえた「保険提案のヒアリング力」
- FP2級の知識を活かした「保障設計の基礎理解と説明力」
- 訪問先で臨機応変に対応する「対面営業力」
- 公的保障との違いを説明する「教育力・説得力」
- 保険業界の営業スタイルに触れた「業界理解と価値観の再整理」
🏠 不動産チェーンの立ち上げメンバーとして“住まいのプロ”を学ぶ
40代後半に入ってからの挑戦です。
地元の企業が不動産業に参入するためフランチャイズの不動産チェーン店を立ち上げ、私はそのタイミングで入社しました。
業界未経験ながら、これまでの営業経験や人と接するスキルを活かして、「住まいを扱う仕事」に挑戦することにしたのです。
取り扱っていたのは、新築建売住宅、土地、中古住宅、中古マンションといった売買物件。
購入したい人・売却したい人、どちらのお客様にも対応する営業スタイルでした。
営業手法は飛び込みではなく、スーモやアットホームなどの不動産系WEB媒体、新聞折込チラシ、ポスティングを活用した反響営業が中心。
自分たちでチラシをポスティングしたり、掲載物件の選定や写真撮影、掲載許可の確認、原稿の校正なども営業の仕事としてこなしていました。
来店されたお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、条件に合う物件を提案。
内見の案内から価格交渉、ローン審査、契約の流れまで、不動産取引に必要な知識を一から学び、実践の中で吸収していきました。
また、「家を売りたい」というお客様に対しては、現在の住まいや土地の状況を確認し、近隣相場や過去の取引事例をもとに査定・販売価格をご提案。
掲載のご承諾をいただいた物件は、魅力が伝わるよう写真や原稿にこだわり、売主様の想いもくみ取った対応を意識していました。
このチェーンでは研修制度もユニークで、ロールプレイやロジックトークなど、“型”としての営業をしっかり身につけられる環境がありました。
物件の良し悪しだけでなく、お客様が「どこで暮らすか」「どういう暮らしをしたいか」といった、感情面にも寄り添う提案ができるよう意識していました。
高額かつ人生に影響する「住まい」という買い物を扱う仕事は、プレッシャーも大きい反面、契約が決まったときの喜びや、「ありがとう」と言ってもらえたときの嬉しさは格別でした。
📌 この仕事で得たスキル
- 反響営業による問合せ対応力と初動対応のスピード感
- 物件確認・撮影・掲載調整などの広告実務スキル
- ローン審査の流れや返済計画に関する資金知識と説明力
- 購入・売却の両面対応で養われた提案力と交渉力
- 重要事項説明や契約に関わる書類実務の基礎知識
- “住まい”を軸にしたライフスタイル提案力
- 高額商材を扱う中での信頼関係構築スキル
- フランチャイズならではの営業トーク・ロジック習得
🏗 建築会社への転籍と“工事部門”での実務経験
40代後半、再び現場寄りの仕事に挑戦することになりました。
不動産チェーンの立ち上げに関わっていた会社が、不動産事業から撤退することが決まり、
そのタイミングで、同じ市内で同フランチャイズの不動産チェーンを展開していた建築会社に事業が譲渡され、私も転籍することとなりました。
新しい職場では仲介売買の部門と、工事部門が併存しており、私は過去のリフォーム経験を買われ、工事部門に配属されました。
現場の責任者1名と私、そして時々社長も現場に出てくるという、かなり小回りの効く体制でのスタートでした。
最初のうちは、責任者の補助として現場に同行し、工具を運んだり、施工のお手伝いをしながら現場感覚を掴むところからのスタート。
業務に慣れるにつれ、お客様対応や見積もり、工程調整などの実務も徐々に任されるようになっていきました。
メインで扱っていたのは、不動産仲介部門が販売した新築建売住宅の購入者向けの追加工事(カーポート設置など)や、中古住宅の購入者によるリフォーム案件。
工事内容のヒアリングから業者手配、見積もり作成、工事完了後のチェックまで、一通りの流れを経験しました。
また、戸建て住宅を解体して更地にする工事も一部担当しており、残置物の撤去、廃材の分別、業者との段取り調整など、解体工事特有の注意点や手続きについても学ぶことができました。
その中でも印象的だったのがアスベストの存在です。
築年数の古い建物を解体する際、アスベストが使われているかどうかの確認は必須であり、含有が判明した場合は専門業者による対応が必要となり、費用や工程、手続き面でかなり大変なことになると実感しました。
「見えないリスク」への意識がグッと高まった経験でもあります。
さらに、公共工事の業者登録も行っていたため、小学校や消防署などの小規模な改修工事も多く手がけていました。
私は、各施設の担当課(例:学校施設課や消防施設課)のご担当者にご挨拶へ伺い、現場確認や見積もり提案といった営業的な役割も担っていました。
仲介売買部門が人手不足のときには、新築建売住宅の内覧会や現地案内のヘルプにも入るなど、部署を超えたサポートも柔軟に行っていました。
この会社は新築戸建ての建築も手がけていたため、現場の手伝いや写真撮影などを通じて、基礎工事から建前、完成までの一連の流れを見ることもできました。
リフォーム中心だった私にとって、家づくりの“最初から最後まで”を実際に見られたことは、視野を広げる大きな経験となりました。
📌 この仕事で得たスキル
- 追加工事やリフォームに関する提案力と見積もり作成スキル
- 小規模工事における現場調整や施工スケジュール管理力
- 解体工事に関する知識と残置物処理、アスベスト対応の基礎理解
- 現場責任者の補助から得た実践的な施工知識と段取り力
- 公共施設工事における施設担当者との交渉・営業スキル
- 新築戸建ての工程理解と建築知識の基礎
- 部門間連携による柔軟な業務対応力
🧱 建材・住宅設備の卸会社で、“営業×現場監督”を兼任
50歳手前で、“営業”と“現場監督”の両輪を担う働き方に挑戦しました。
次に勤めたのは、建築資材や住宅設備、住宅部材などの卸売販売や、リフォーム、改修工事をおこなう会社でした。
取り扱う商材や工事の内容が幅広く、B to C(個人宅向け)とB to B(法人向け)の両方を手がけていたため、私の業務も多岐にわたるものでした。
B to Cの案件では、キッチンや浴室などの水回り設備のリフォーム、内装工事、さらにはカーポートやフェンスなど外構工事まで、多様なご依頼に対応。
「キッチンをきれいにしたい」「浴室を快適にしたい」といった日々の生活に直結するご相談が中心でした。
私は、現地調査から見積もり、商品提案、工事手配、工事後の完了確認まですべてを一貫して担当。
つまり、自分で受注した案件を自分で現場監督として動かすというスタイルです。
商品の選定には、現場の状況やお客様のご希望を踏まえたうえで、メーカーごとの仕様や施工条件なども考慮する必要があり、
単なる営業というよりも“実務に即した知識を持つ相談相手”のような立ち位置を意識していました。
B to Bの業務では、工務店や設計事務所、地元企業の担当を持ち、依頼のあった商品の提案、見積もり、受注処理、納品手配までを一通り対応。
必要に応じて現場にも足を運び、現地調査や納まりを確認しながら、最適な製品選定を行っていました。
また、事務所や工場のリフォーム、改修工事、拡張工事などのご依頼もあり、こちらも見積もりから業者手配、現場管理までを担当。
特に工場では、稼働を止めずに工事を進める必要があることも多く、安全対策や搬入・施工のタイミングには細心の注意を払って対応していました。
このように工事全体を見ながら動くうえで難しかったのが、
「いただいた工事内容に対して、どの職人・業者に相談すべきかを判断すること」。
ですが、さまざまな現場を経験するなかで、多様な職人さんや協力業者さんと知り合う機会が増え、
相談できる幅がぐっと広がったのは、この仕事を通して得た大きな財産でした。
さらにこの会社では、建築工事だけでなく土木関連の工事にも対応しており、駐車場の整備や側溝工事などの案件もありました。
元請けとして動くこともあれば、他社からの依頼で下請け業者として施工を請け負うケースもあり、両方の立場で仕事を進める機会があったのも特徴的でした。
現場監督としては、工程表の作成や進捗確認、職人や業者の手配、トラブル時の調整など、現場全体を俯瞰しながら動く必要がありました。
現場でのちょっとした気配りや判断力が求められることも多く、建材や住宅設備に関する知識と、現場での肌感覚の両方が求められるポジションでした。
📌 この仕事で得たスキル
- 個人宅リフォーム・外構工事などの提案から現場管理までの一貫対応力
- キッチン・浴室・設備機器に関する製品知識と実務的アドバイス力
- 工務店・設計事務所・企業担当としての営業スキル(提案〜納品手配)
- 事務所・工場の改修工事に関する現場管理力と安全配慮スキル
- 工事内容に応じた適切な職人・業者選定の判断力とネットワーク構築力
- 土木関連工事(駐車場整備・側溝工事など)の段取り・業者調整スキル
- 元請け・下請け両面の現場経験と立場に応じた対応力
- 工程表作成、進行管理、業者手配など現場監督としての実務スキル
- トラブル発生時の即時対応・現場判断力
- 商品知識に裏打ちされた、現場目線の営業提案力
🎬 スキル棚卸しを終えて感じたこと
こうしてあらためて過去を振り返ってみると、「あのときのあれが、今のここにつながってたのか」と驚く場面がいくつもありました。
一見バラバラに見える転職歴でも、実は共通するスキルや価値観、得意なスタイルのようなものがちゃんとあって、
「自分ってこういうタイプなんだな」とあらためて気づくきっかけにもなりました。
履歴書じゃ伝えきれないスキルや経験って、いっぱいある。
でも、こうして言語化していけば、きっと誰かに伝わるものになる。
そしてなにより、どの経験もぜんぶ“無駄じゃなかった”と、ようやく胸を張って言える気がしています。
──どおりで、浅く広く知識があるわけだ(笑)
もし今、「自分のスキルって何なんだろう…」と迷っている方がいたら、
このスキル棚卸しシリーズが、ちょっとしたヒントになれば嬉しいです。
🎉 最後までお読みいただきありがとうございました。
このスキル棚卸しシリーズは、自分のキャリアを振り返りながら書いた記録です。少しでも参考になればうれしいです。
📚 スキル棚卸しシリーズまとめリンク
👉 【前編】10代〜20代|現場力と実践力の原点
👉 【中編】30代〜40代前半|視野が広がった葛藤と成長の時期
👉 【後編】40代後半〜50代|住宅×現場×営業スキルの集大成
👉 【まとめ編】スキル棚卸しをやってみた結果…全職歴から見えてきた“自分の軸”とは?